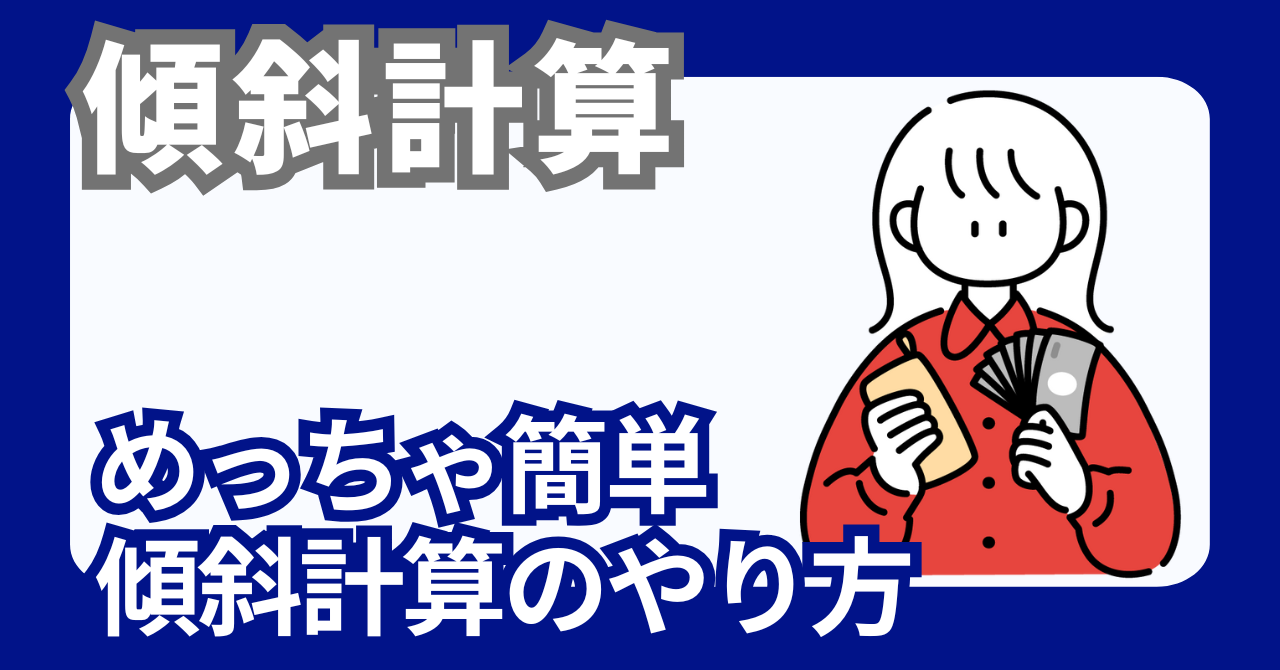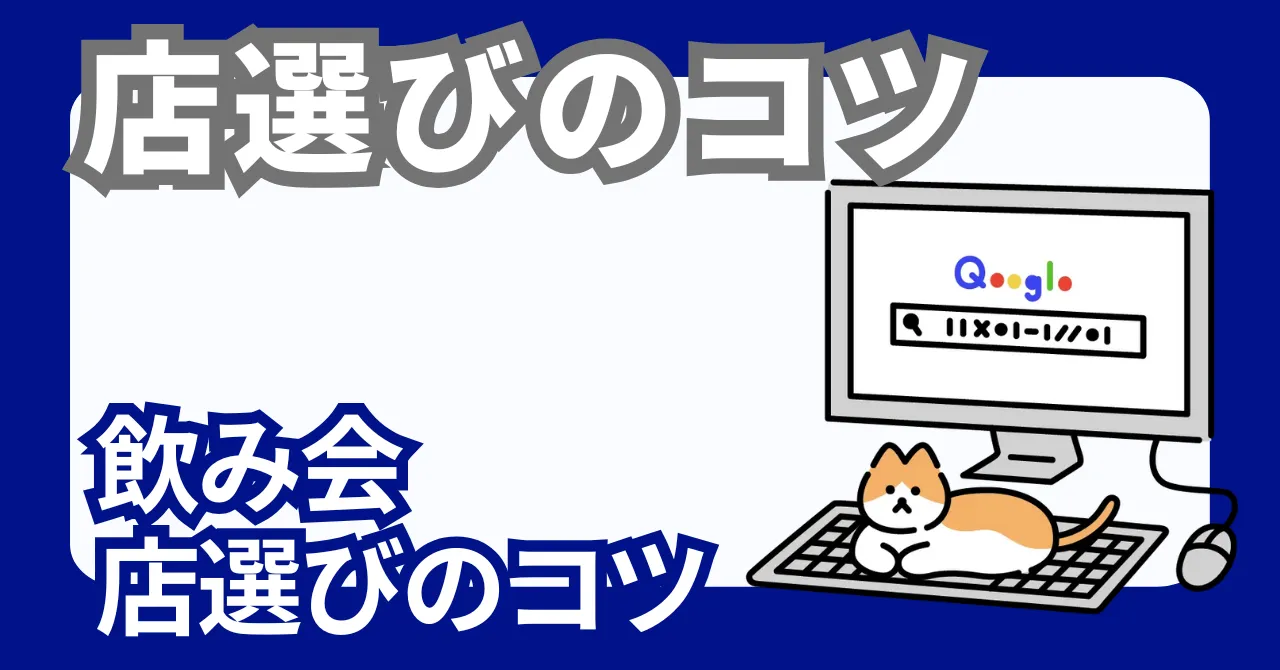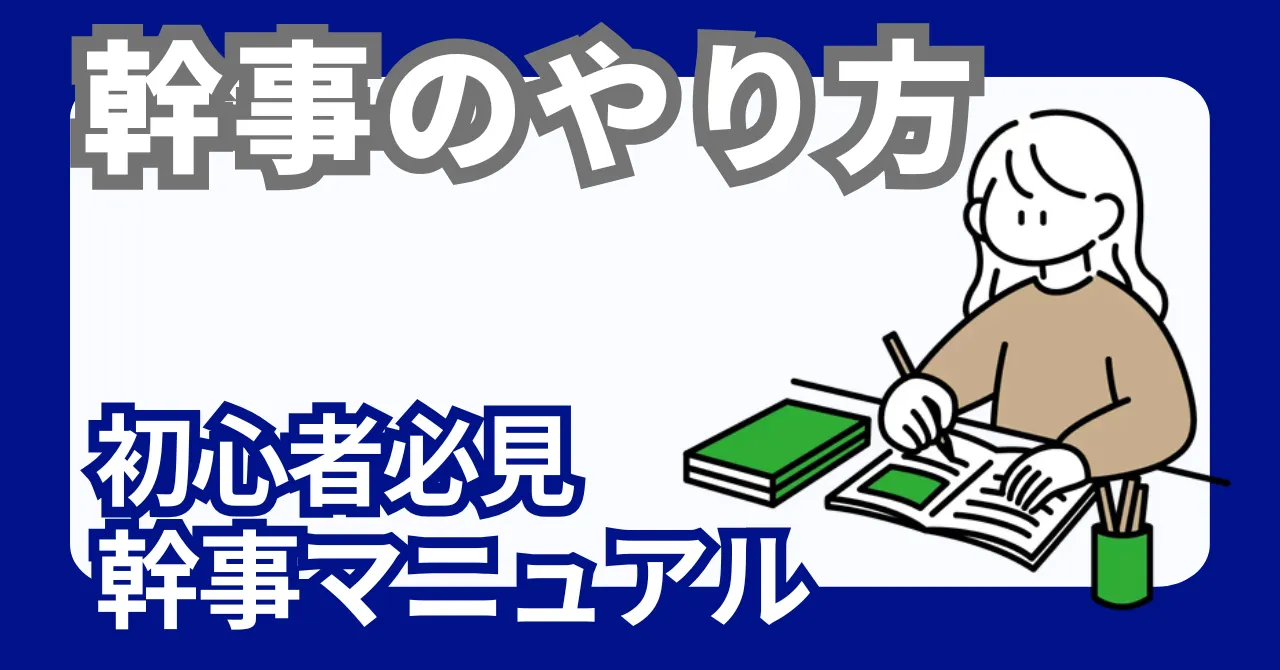そも
傾斜計算とは、
- 若手社員の
金銭的負担の 軽減、上司の 立場尊重 - 主役を
祝う ため奢る
どうやって
傾斜計算を
役職・立場別の
負担割合は、
| 役職・立場 | 負担割合の | 例: 割り勘が 5000円の | 補足 |
|---|---|---|---|
| 送歓迎の | 0%~50% | 0~2500円 | 主役は |
| 若手社員 | 50%~100% | 2500~5000円 | 基本料金から |
| 中堅社員 | 80%~120% | 4000~6000円 | 基本料金の |
| 管理職 / 部 | 100%~200% | 5000~10000円 | 全体の |
いい
Excelで
個人的な
傾斜計算は
おすすめアプリ - いい
参加者を
以下は
ベテラン: 田中、先輩や
ぜ
どうしても
どうしても
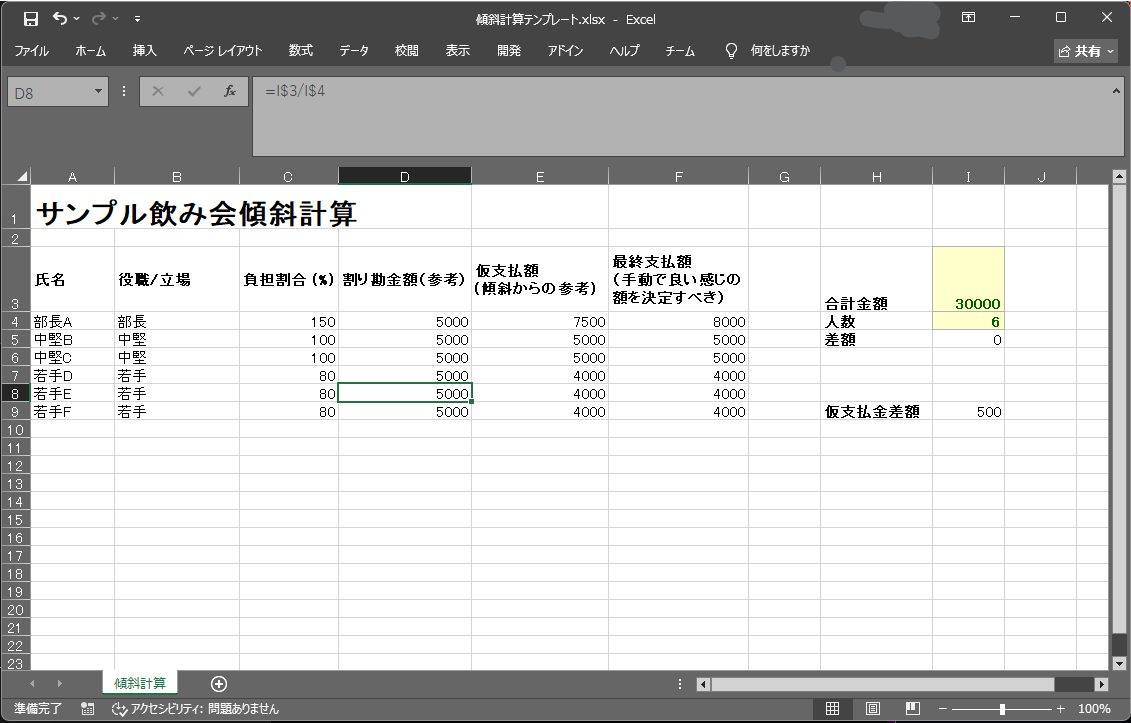
ダウンロード: 傾斜計算テンプレート.xlsx
負担割合を
具体的な
【設定例】
- 合計金額: 30,000円
- 参加者: 6名
(部 長1名、 中堅2名、 若手3名)
ステップ1:1人あたりの
まず、
30,000円 ÷ 6人 = 5,000円
→ 基本料金は
ステップ2:各役職の
ステップ1の
-
負担割合の
設定 (例) : - 部
長: 150% - 中堅: 100%
- 若手: 80%
- 部
-
支払額の
仮計算: - 部
長: 5,000円 × 150% = 7,500円 - 中堅: 5,000円 × 100% = 5,000円
- 若手: 5,000円 × 80% = 4,000円
- 部
ステップ3:合計金額が
仮計算した
(部長7,500円×1)+(中堅5,000円×2)+(若手4,000円×3)= 29,500円
合計30,000円に
- 最終的な
支払額: - 部
長: 7,500円 + 500円 = 8,000円 - 中堅: 5,000円
- 若手: 4,000円
- 部
これで、
円滑に
傾斜計算を
負担割合の
相談の
Excelや
事前に
まとめ
傾斜計算は、
- 「負担割合
(%)」を 基準に すると 計算が 分かりやすい。 - アプリや
Excelを 使って ラクに 計算しよう。 - 計算手順は「基本料金の
算出 → 仮計算 → 最終調整」の 3ステップ。 - 最も
重要なのは、 割合案が できた 段階での「上司・先輩への 事前相談」。
この